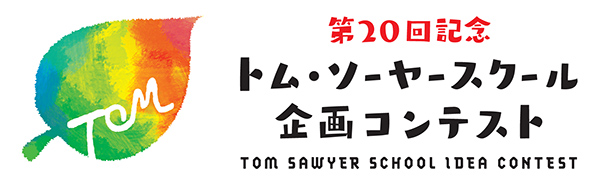
|
速報レポート3 7月前半の活動
「日本遺産の「室津港」を見学しよう (7月12日)」
この日は,学校からバスで50分ほど南にある「室津のまちなみ」を見学しました。室津港は,江戸時代の北前船の寄港地としてたつの市で唯一の日本遺産に選ばれています。その構成文化財を見学することが目的です。例えば,現在の「もやい(綱)」の様子や明治時代までのもやい石をチェックしたり,湊口御番所跡を見学したりしました。また,賀茂神社や姫路藩茶屋など北前船だけでなく,国指定文化財にも注目した時間となりました。





学校に帰り,さっそく撮影記録の整理とともに,「なぜ室津が日本遺産に選ばれたのかな」を問いとして,分析を始めました。みんなの個別の意見を整理すると,「室津の港」,「神社」の2つを根拠にして考えることになりました。
例えば「もやい石」からだと多くの船が出入りしたとの考えが多く出ました。そうなると,それらの入港を確認する場所が必要だと気付きます。それが「湊口御番所」の役割です。見学したことで得た情報が知識としてどんどんつながっていきました。授業の最後は播磨国風土記の「この泊,風を防ぐこと,室のごとし」の一文から,地形の特長についても議論できました。
見学したことをどう学習に活かすのかによって,思考する力,得る知識の量は変わっていきます。今後も,みんなの「なぜ」をしっかりとつないでいきたいです。


「泥窯づくりをしよう (7月14日)」



国指定新宮宮内遺跡で泥窯づくりをしました。これは,弥生時代とほぼ同様の方法です。男女の人数がほぼ同じであるため,男女別に2つの窯をつくります。
まず,みんなは埋蔵文化財センターの先生のお話を聞き,土と水を混ぜながら壁土をつくりました。次に,土台となる木枠ができれば,1カ月ほど乾かした土器を台にのせていきます。そして,わらで窯の原型をつくり,壁土を約3cmの厚さで塗っていくのです。特に男子は,センターの先生が女子にアドバイスするのを聞きつつ,ほぼ自分たちの力で窯をつくり上げました。
午後,まさかの雷雨に見舞われ,心配しましたが,しっかりと燃えていました。特に女子の窯は安定した燃え方をしていました。



「窯出し!大成功 (7月15日)」



本来であれば16日が窯出しでしたが,前日の雨も影響し,窯が壊れていたため,1日はやく窯だしをしました。

雨の影響があるのではないかとみんなはとても心配しましたが,なんと奇跡的に大成功となりました。窯が崩れた場合は,土器が割れることもあるのですが,これも問題なしでした。みんなの幸運に感激しています。
土器とともにとった写真からも満足感いっぱいの笑顔が印象的でした。「展覧会をしたいなあ。」との声もあり,もしかすると行うかもしれません。夏休み中は,陰干しでさらに良い仕上げにしたいと思います。
速報レポート1 4~5月の活動
速報レポート2 6月の活動
速報レポート4
速報レポート5
速報レポート6
■別年度のレポート
2017年度 キラ☆まち日記~メイ・ジンからのおくりもの~ 実施レポート
2015年度 人も自然も笑顔の楽園プロジェクト 実施レポート